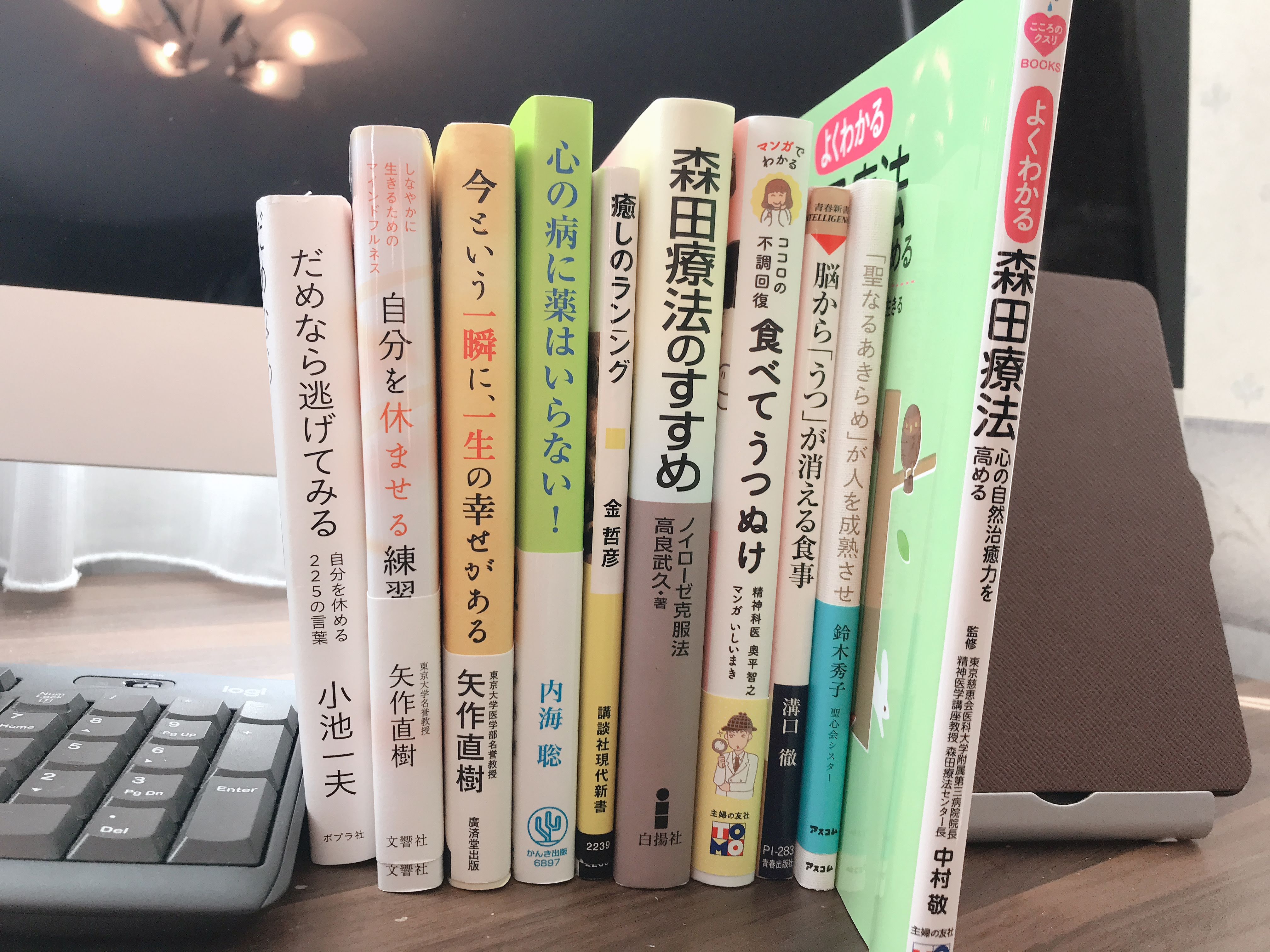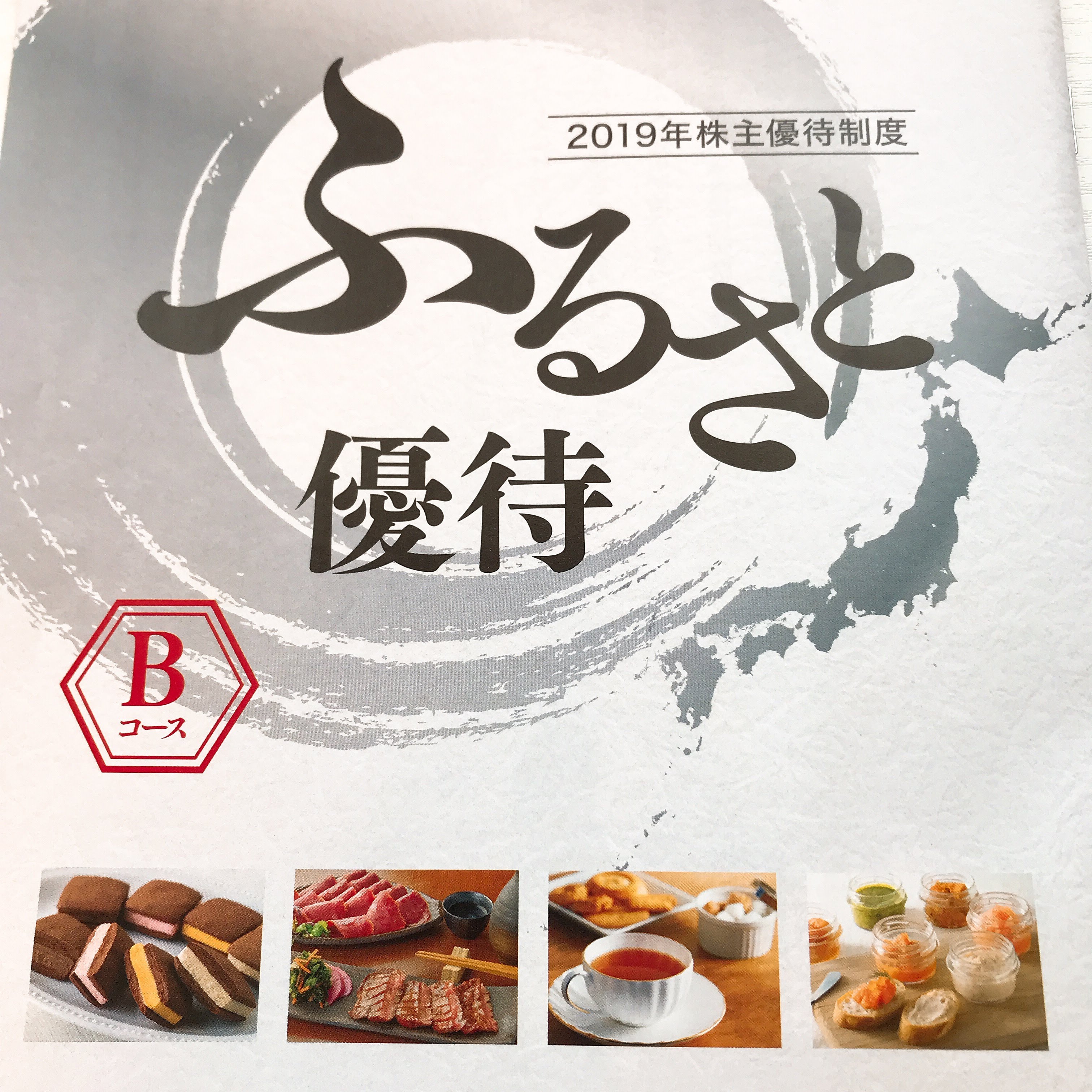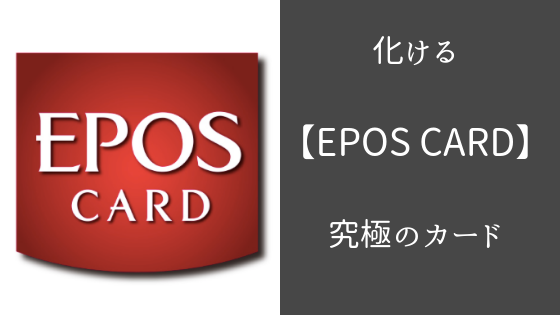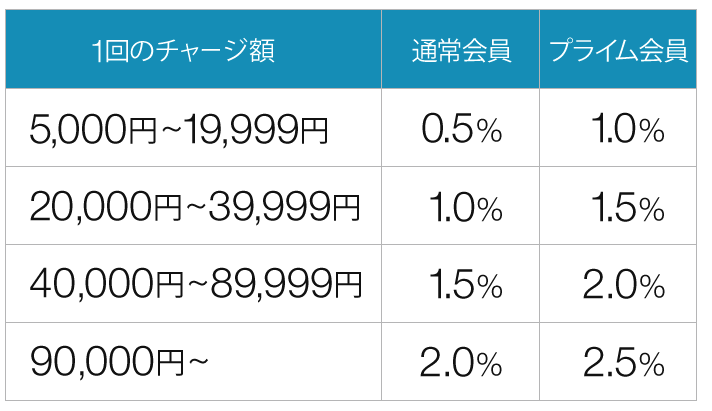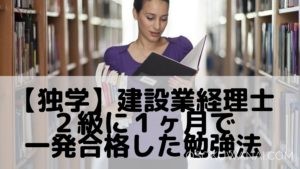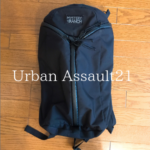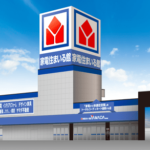どうも、チャンドラーです。
先日建設業経理士2級を受験してきました。
今回の試験は特に簡単だったため、自己採点で100点満点を取ることができました。(建設業経理士は点数の結果公開がないため、あくまで点数は自己採点で推測するしかない試験です)
無事合格の建設業経理士2級ですが、そもそもこの資格の合格率・難易度はどれくらいのものなのか本記事で検証してみます。
まだ未受験の方は参考にしていただければと思います。
もくじ
直近10回の合格率分析
まずは直近10回の合格率を見てみましょう。
第26回(令和元年 9月8日実施):41.4%
第25回(平成31年 3月10日実施):30.8%
第24回(平成30年 9月9日実施):33.7%
第23回(平成30年 3月11日実施):44.7%
第22回(平成29年 9月10日実施):37.2%
第21回 (平成29年 3月実施):33.93%
第20回 (平成28年 9月実施):50.83%
第19回 (平成28年 3月実施):38.46%
第18回 (平成27年 9月実施):30.83%
第17回 (平成27年 3月実施):35.10%
直近10回の平均合格率は37.69%となっています。
ちなみに日商簿記2級の最近の平均合格率は23.7%です。
3人に1人以上が合格している試験であることが分かります、更に受験機会は年に2回あることを勘案するとそこまで難易度は高くないと思われます。
建設業経理士2級の問題難易度

個人的な所感としては日商簿記3級に毛が生えた程度だと思っています。
昨今の連結会計の難問が出される日商簿記2級の難化とは比べ物になりません。
難易度的に言うと日商簿記2級>>>建設業経理士2級>日商簿記3級ぐらいではないでしょうか。
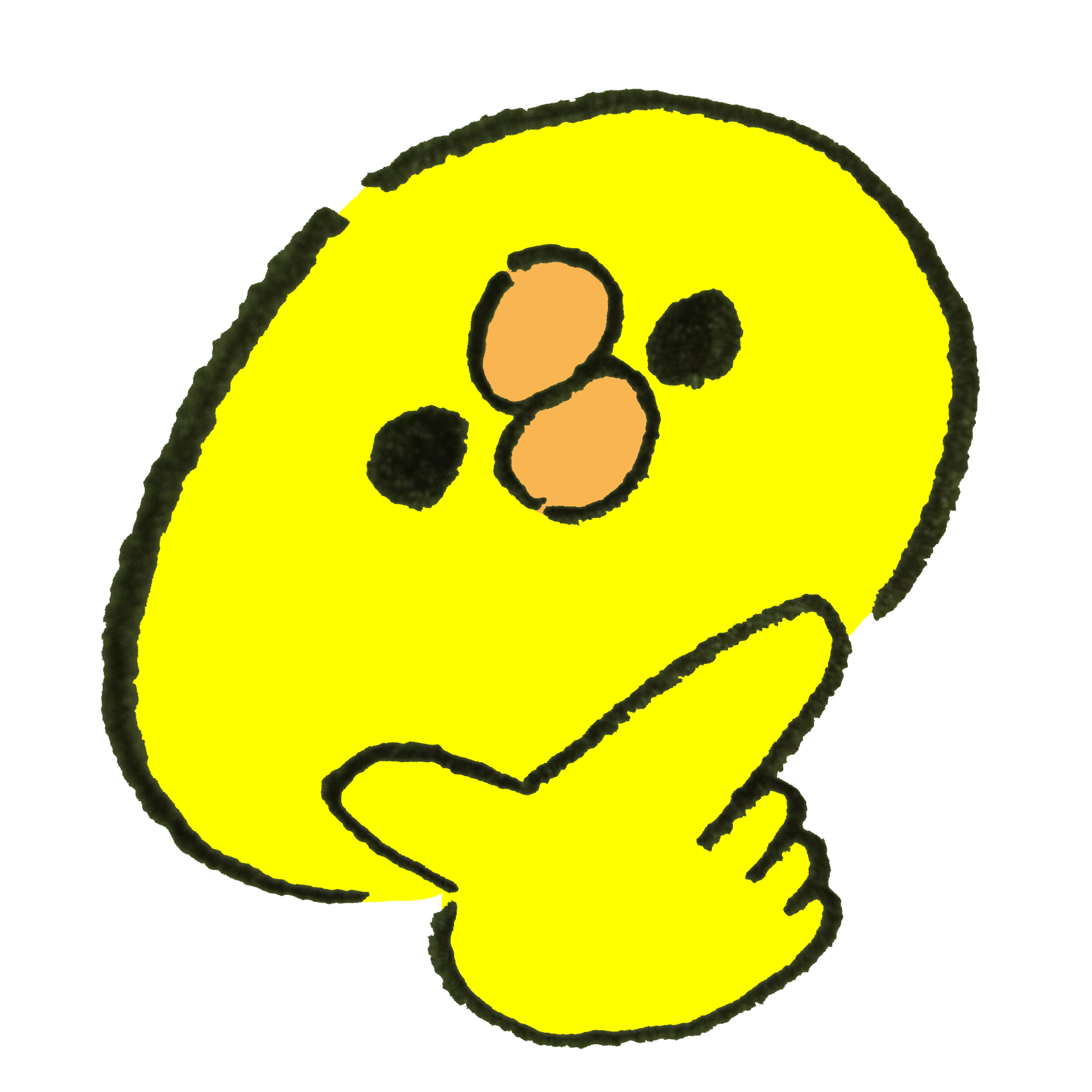
と思いきや、残念ながらそうは問屋がおろしません。
建設業経理士2級の試験には工業簿記の知識がちょこっと必要だからです。
簿記3級ではあくまで街の個人商店的な簿記知識までしか習えませんから、どうしても簿記2級の範囲で学ぶような中小企業の経理を想定した簿記知識がマストになります。
例えばめちゃくちゃ頻繁に使う勘定科目として「未成工事支出金」というものがあるのですが、これは工業簿記の「仕掛品」に相当します。
「仕掛品」の概念は少し慣れが必要で簿記2級を勉強した人なら「未成工事支出金」も楽勝なのですが、未学習の方がいきなりこの勘定科目を覚えるのはひょっとすると多少苦戦するかもしれません。
だからと言って日商簿記2級の範囲のような、結構広範囲な工業簿記の知識は全く必要ありません。(シュラッター図のような難解な解法は一切なし、かなり楽です)
そう考えるとあくまで会社的・就活的に建設業経理士2級だけ取得できればOKな場合、日商簿記3級合格→建設業経理士2級勉強開始が最短ルートかと思います。
「未成工事支出金」以外にも建設業経理士の試験にしか出てこない勘定科目がいくつかありますが、せいぜい6〜7個程度なので覚えるのは結構楽勝です。
建設業経理士2級の転職影響力
建設業経理士2級は日商簿記2級と比べるとハローワークで求められる可能性は天と地ほどあります。
肌感覚で言うと日商簿記2級を求められる求人が100あるとすると、建設業経理士2級は5程度でしょうか。

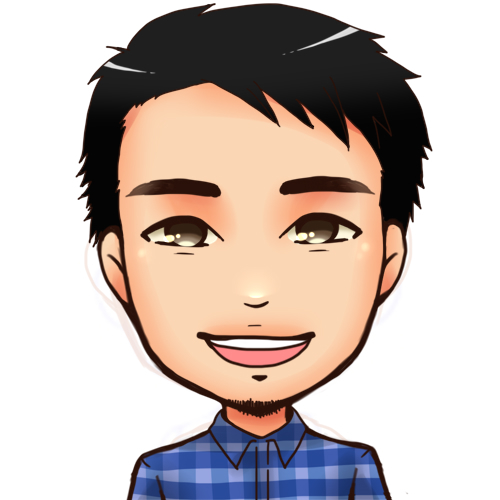
日商簿記2級やあれだけ難しい1級を持っていても、残念ながら会社が仕事を取りやすくなったり対外的に加点になることはありません。
しかし建設業経理士2級は入札工事において加点になります。
ましてや建設業経理士1級になると、税理士や公認会計士が社内にいるのと同等の加点になるのです。
そのため建設業経理士は特定の分野において喉から手が出るほど欲しい人材であると言っていいでしょう。
しかしもし業界範囲を狭めたくないのであれば、僕がやったように日商簿記2級とのダブルライセンスが一番好ましいかもしれませんね。
まとめ

簿記の資格自体不況にも強いと言われていますが、建設業経理士2級は建設業においていつの時代も需要がある難易度的にもコスパ抜群の資格であると感じています。
簿記を勉強している方であれば、是非取ってみて欲しい資格です。合格率・難易度的にも少し頑張れば独学で絶対に合格できますよ。

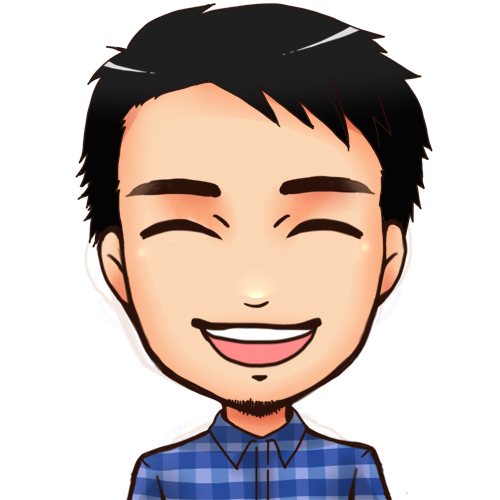
どうも、チャンドラーでした。